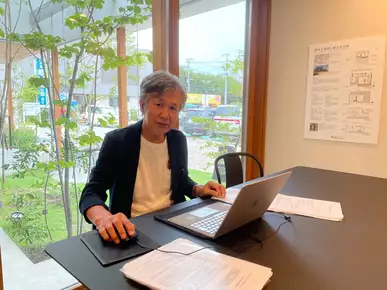断熱材について

断熱材の役割と種類、選び方について詳しく解説します。
断熱材とは
熱は、非常に伝わりやすい性質をもっているため、建物の外壁を通して室内外を行き来します。特に対策をとっていない住宅では、冷暖房を使用して室内の温度を調節したとしても、壁を通して熱が行き来してしまうため、室温を一定に保ちにくく、より多くのエネルギーを消費し続けてしまうのです。
断熱材は、建物に設置することで熱の屋内外への移動を遮断します。熱を伝わりにくくすることで、室内の温度が保ちやすくなるのです。
断熱材は、建物に設置することで熱の屋内外への移動を遮断します。熱を伝わりにくくすることで、室内の温度が保ちやすくなるのです。
断熱材の種類・選び方
断熱材は、無機繊維系・木質繊維系・天然素材系・発砲プラスチック系といった4つの種類に分類されています。
無機繊維系の「グラスウール」や「ロックウール」は、燃えにくいが湿気には弱いという点が大きな特徴。木質繊維系の「セルロースファイバー」は、結露を防ぎやすく防音効果もありますが、価格が高めの素材です。天然素材系の「ウールブレス」と「炭化コルク」は、羊毛やコルク栓の端材といった自然に優しい原料からできています。発砲プラスチック系の素材は、「硬質ウレタンフォーム」「ポリスチレンフォーム」「フェノールフォーム」の3種類。ほかの断熱材と比べて熱の伝わりやすさを表す熱伝導率が低めで、高い断熱性があります。
一般的によく使用される断熱材は、ビニール袋に綿を詰めたような形状になっているグラスウールです。こちらの断熱材は壁の中へと詰めていきますが、隅の狭い部分まではカバーしきれません。しかも、きちんと施工できていなければ、結露が発生して柱や骨組みとなっている木材を腐らせてしまう可能性があるのです。
建物の寿命を早めないためにも、すき間なく敷き詰められる断熱材を選びましょう。木質繊維系の「セルロースファイバー」や、発砲プラスチック系の「ウレタンフォーム」などの断熱材がおすすめです。
>>断熱性能の違いで室温や光熱費はどう変わる?詳しくはこちら!
無機繊維系の「グラスウール」や「ロックウール」は、燃えにくいが湿気には弱いという点が大きな特徴。木質繊維系の「セルロースファイバー」は、結露を防ぎやすく防音効果もありますが、価格が高めの素材です。天然素材系の「ウールブレス」と「炭化コルク」は、羊毛やコルク栓の端材といった自然に優しい原料からできています。発砲プラスチック系の素材は、「硬質ウレタンフォーム」「ポリスチレンフォーム」「フェノールフォーム」の3種類。ほかの断熱材と比べて熱の伝わりやすさを表す熱伝導率が低めで、高い断熱性があります。
一般的によく使用される断熱材は、ビニール袋に綿を詰めたような形状になっているグラスウールです。こちらの断熱材は壁の中へと詰めていきますが、隅の狭い部分まではカバーしきれません。しかも、きちんと施工できていなければ、結露が発生して柱や骨組みとなっている木材を腐らせてしまう可能性があるのです。
建物の寿命を早めないためにも、すき間なく敷き詰められる断熱材を選びましょう。木質繊維系の「セルロースファイバー」や、発砲プラスチック系の「ウレタンフォーム」などの断熱材がおすすめです。
>>断熱性能の違いで室温や光熱費はどう変わる?詳しくはこちら!
窓について

高気密・高断熱な家づくりのカギとなる窓選びについて解説しましょう。
窓枠の種類・選び方
窓の断熱性は、窓枠の種類によっても変わります。断熱性が低い窓枠は、アルミサッシである場合が多いです。アルミ製の窓枠は耐久性に優れているところがメリットですが、結露が発生しやすいというデメリットもあります。
そのアルミのメリットを残しつつ結露も起こりにくい窓枠として登場したのが、アルミと樹脂を取り入れた複合サッシです。室外側に耐久性の優れたアルミ、室内側に結露が発生しにくい樹脂を備えることで、断熱性の低さの象徴でもある結露の発生を抑えることができます。断熱性を重視するなら、窓枠に使用される素材にも注目してみましょう。
そのアルミのメリットを残しつつ結露も起こりにくい窓枠として登場したのが、アルミと樹脂を取り入れた複合サッシです。室外側に耐久性の優れたアルミ、室内側に結露が発生しにくい樹脂を備えることで、断熱性の低さの象徴でもある結露の発生を抑えることができます。断熱性を重視するなら、窓枠に使用される素材にも注目してみましょう。
窓ガラスの種類・選び方
窓ガラスは、素材そのものが熱を伝えやすい性質をもっています。そのため、耐熱性を高めるためには、ガラスを複数枚重ねた製品を選ぶことがおすすめです。
近年では、ペアガラスと呼ばれる、2枚のガラスを重ねた窓を採用している住宅も増えてきています。その中でも、2枚のガラスの間が真空状態となっているタイプは、より耐熱性に優れている製品です。
また、耐熱性に優れた窓には、3枚のガラスを重ね合わせた製品もあります。コストとの兼ね合いも考慮して、十分な耐熱性能を備えた窓ガラスを選んでみましょう。
>>注文住宅の断熱を高めるにはどんな方法がある?詳しくはこちら!
近年では、ペアガラスと呼ばれる、2枚のガラスを重ねた窓を採用している住宅も増えてきています。その中でも、2枚のガラスの間が真空状態となっているタイプは、より耐熱性に優れている製品です。
また、耐熱性に優れた窓には、3枚のガラスを重ね合わせた製品もあります。コストとの兼ね合いも考慮して、十分な耐熱性能を備えた窓ガラスを選んでみましょう。
>>注文住宅の断熱を高めるにはどんな方法がある?詳しくはこちら!
省エネ基準とは

省エネ基準を構成している、2つの基準について解説しましょう。
一次エネルギー消費量の基準
一次エネルギーの消費量とは、冷暖房・給湯・換気・照明・家電といった住宅内の設備によって消費するエネルギー量のことを指します。
省エネ基準を満たすためには、この一次エネルギー消費量に定められた基準値をクリアしておく必要があるのです。基準値は、建物を建てる地域や建物の床面積などの条件によっても変わります。
省エネ基準を満たすためには、この一次エネルギー消費量に定められた基準値をクリアしておく必要があるのです。基準値は、建物を建てる地域や建物の床面積などの条件によっても変わります。
外皮熱性能の基準
外皮熱性能は、断熱性を示すUA値と、窓から入る太陽熱をどの程度遮れるのかを示すηAC値より評価されます。この2つの数値が基準値をクリアしていることも、省エネ基準を満たすための条件なのです。
UA値とは
UA値とは、外皮平均熱貫流率のことを意味しています。この数値は、建物の壁や床、屋根などから外へと逃げる熱量を建物全体の表面面積で割って算出した値です。
UA値の数値が低ければ低いほど、室内の熱を外へ逃がしにくく、耐熱性や気密性が高いことを表しています。
UA値の数値が低ければ低いほど、室内の熱を外へ逃がしにくく、耐熱性や気密性が高いことを表しています。
千葉市花見川区・八千代市・柏市の省エネ基準地域区分
省エネ基準は、地域によっても異なります。同じ冷暖房設備を備えた住宅でも、気候の異なる地域では同じように快適に過ごせない可能性があるため、気候に応じた基準を設定しています。この地域区分は、2019年11月に改正されました。
千葉市花見川区・八千代市・柏市エリアの省エネ基準地域区分は、6地域です。北海道をはじめとした1地域に近いほどUA値の基準は低く、沖縄の8地域に近いほどUA値の基準は高くなります。
千葉市花見川区・八千代市・柏市エリアの省エネ基準地域区分は、6地域です。北海道をはじめとした1地域に近いほどUA値の基準は低く、沖縄の8地域に近いほどUA値の基準は高くなります。
ZEH基準とUA値

千葉市花見川区・八千代市・柏市のZEH基準を満たすUA値もあわせてチェックしておきましょう。
ZEH基準とは
ZEH基準は、より高いUA値の基準を満たしていることや太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーが導入されていること、再生可能エネルギーによって基準一次エネルギーの消費量を全て削減できているかなどのポイントをクリアする必要があります。
省エネ基準よりも厳しいZEH基準を満たしている住宅は、高い断熱性だけでなく環境にも優しい機能を兼ね備えた住宅といえるでしょう。
省エネ基準よりも厳しいZEH基準を満たしている住宅は、高い断熱性だけでなく環境にも優しい機能を兼ね備えた住宅といえるでしょう。
千葉市花見川区・八千代市・柏市のZEH基準を満たすUA値
省エネ基準地域区分の6地域に分類される千葉県千葉市・八千代市・柏市では、通常の省エネ基準で0.87のUA値を満たしていなければなりません。さらに、ZEH基準を満たす場合には、0.6のUA値をクリアしておく必要があります。
通常の基準よりも2割以上高い数値となっているZEH基準を満たしておくことで、十分に高い気密性と断熱性が期待できるでしょう。
>>ZEHの基準をはるかに上回るR+houseの断熱性能とは?
通常の基準よりも2割以上高い数値となっているZEH基準を満たしておくことで、十分に高い気密性と断熱性が期待できるでしょう。
>>ZEHの基準をはるかに上回るR+houseの断熱性能とは?
千葉県内で省エネ住宅を建てるなら「R+house八千代・幕張・柏・守谷」へ!

千葉県内で新築で注文住宅を建てる際に高気密・高断熱な省エネ住宅をご検討中の方は、R+house八千代・幕張・柏・守谷へお気軽にご相談ください。
>>高気密住宅・高断熱住宅ってどんな家?メリット・デメリットをご紹介