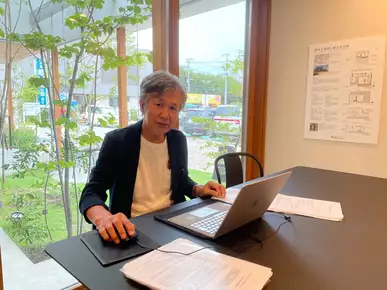家の性能とは?
良い家とは、どのような家のことを言うのでしょうか。デザイン性の高さや間取りなども重要ですが、コロナ禍の影響でおうち時間が増えたことにより、昨今は家の「性能」を重視する人が増えてきています。そうは言っても、性能のどのようなところにこだわれば良いのかは、個人によって意見が分かれるところ。そこで重要なのが「住宅性能表示制度」です。
ここでは、住宅性能表示制度とはどんな制度なのか、どう活用したら良いのかについて詳しく解説します。
ここでは、住宅性能表示制度とはどんな制度なのか、どう活用したら良いのかについて詳しく解説します。
住宅性能表示制度について

住宅性能表示制度には、住宅を建てる前の評価である「設計住宅性能評価」と、建て始めてから受ける評価である「建設住宅性能評価」の2つがあります。
評価項目は「耐久性」「耐震性」「維持管理・更新への配慮」「断熱性・省エネ性」「火災時の安全」「空気環境」「光・視環境」「音環境」「バリアフリー性」「防犯」に関する10の分野から成り立っています。
中でも「耐久性」「耐震性」「維持管理・更新」「断熱性・省エネ性」は必須項目となっており、家づくりで特に重視したい項目です。
基本性能の高い家はメリットだらけ!
良い家を判断する基準は人によって異なりますが、住宅性能表示制度は第三者の専門家によって公正にチェックされています。つまり、客観的に見て「良い家」であるということ。
断熱性の低い家は、結露によるカビが発生しやすいことや、温度差によるヒートショックで亡くなる方が多いことがわかっています。高断熱であることは、家の中が快適であるだけでなく、健康にとっても良い家なのです。
また、省エネルギー性も外せないポイント。省エネルギー性の高い家であればあるほど、冷暖房にかかる光熱費を下げられます。
ほかにも、長期優良住宅や低炭素住宅に当てはまる性能の高い家は、税制優遇や住宅ローン金利の優遇が受けられます。耐震性能の高さによっては地震保険料が割引されるため、基本性能が高いということはそれだけで大きなメリットなのです。
>>建築家と作る高性能住宅「R+house」についてはこちら
>>建築家と作る高性能住宅「R+house」についてはこちら
注文住宅を建築する際は「自分軸」を持つことが大切
住宅性能表示制度は住宅の性能を等級や数値で表したもので、等級に関しては数字の大きさが性能の高さを表しています。全ての分野で数字が高い方が良さそうに見えますが、そうとも限りません。
例えば「明るい家にしたい!」と採光を重視して窓を多く広く取ると、結果として気密断熱性を下げてしまいます。この場合の住宅性能表示では、断熱性で高い等級を取ることはできません。ですが施主様にとっては、断熱性よりも家の明るさを優先した家が、良い家なのです。
つまり、全ての分野で高い等級を取ることが重要ではなく、ライフスタイルや家族構成、地域の気候・風土を加味したうえで、自分にとっての快適な軸を持つことが重要。
ここでは、施主様が自分軸を見つけられるよう、住宅性能表示制度でも必須の項目になっている4つの分野について触れていきます。
耐震性能
耐震性能とは、地震の揺れに対する建物の強度を表す指標のこと。耐震性が高いということは、地震発生時にも傾きにくく、倒れにくい建物であることを表します。耐震等級は1~3までの3段階で評価され、各等級の定義は以下です。
耐震等級1
建築基準法に準じた最低限の耐震性を満たすレベル。震度6~7の地震で即倒壊はしないものの、大規模修繕や建て替えの可能性がある建物を指す。
耐震等級2
震度6~7の地震でも、ある程度の修繕程度で住み続けることが可能。学校や病院などの公共建築がこれに該当する。
耐震等級3
耐久性能
家はどうしても経年劣化していくもの。定期的なメンテナンスは必要ですが、できるだけ劣化を抑えられる家が耐久性能の高い家だと言えます。耐久性を高めるには、柱や土台、外壁などに防腐・防蟻措置を行うこと、基礎部分の高さを確保すること、床下の防湿・換気を行うことが重要です。住宅性能表示における等級は以下の通り。
耐久等級1
建築基準法をクリアするレベルの建物。
耐久等級2
50~60年は、大規模な改修工事が必要ない対策を施した建物。
耐久等級3
75~90年は、大規模な改修工事が必要ない対策を施した建物。
維持管理・更新性能
維持管理・更新性能も、家のメンテナンスに関係した項目です。維持管理・更新性能の高い家は、できるだけメンテナンスしやすい構造となっている家を指します。点検や補修のための点検口が設置されているか、などが評価基準です。各等級の解説は以下の通りです。
維持管理対策等級1
建築基準法をクリアするレベル。
維持管理対策等級2
等級3のa)とb)を実施したもの。
維持管理対策等級3
a)共同住宅などで他の住戸に入ることなく、専用配管の維持管理を行う対策が取られた建物。
b)建物の躯体を傷めずに、点検や補修を行う対策。
c)点検用に開口や掃除口が設置されている。
b)建物の躯体を傷めずに、点検や補修を行う対策。
c)点検用に開口や掃除口が設置されている。
断熱・省エネ性能

省エネ性能に重要なのが、「熱損失係数(Q値)」と「外皮平均熱還流率(UA値)」。Q値やUA値は室内の熱の逃げにくさを数値化しており、数値が小さいほど熱が逃げにくい高気密な建物であることを表しています。
2022年10月時点での住宅性能表示における等級は、以下の通りです。
断熱性能等級1
1988年以前に設定され、現在はなし。
断熱性能等級2
旧省エネ基準で建築された、冬場にかなり寒くなる昔ながらの建物。
断熱性能等級3
新省エネ基準で建設された、一定レベルの断熱性を持つ建物。
断熱性能等級4
次世代の省エネ基準で建設された最高等級の建物。壁や窓、天井、玄関も断熱されていることが条件。
断熱性能等級5
等級4以上の「ZEH水準」と同じ。
断熱性能等級6
2022年10月に施行された新しい等級。一次エネルギー消費量を概ね30%削減可能なレベルの性能が条件。
断熱性能等級7
2022年10月に施行された新しい等級。一次エネルギー消費量を概ね40%削減可能なレベルの性能が条件。
>>夏は涼しく、冬は暖かい住宅に不可欠な高断熱住宅、その秘密とは?
>>快適な住まいを実現するために必要な高気密な家づくりって?
>>断熱性能の違いで室温や光熱費に差が出る?詳しくはこちら!
>>夏は涼しく、冬は暖かい住宅に不可欠な高断熱住宅、その秘密とは?
>>快適な住まいを実現するために必要な高気密な家づくりって?
>>断熱性能の違いで室温や光熱費に差が出る?詳しくはこちら!
千葉市・八千代市・柏市エリア情報

千葉県千葉市・八千代市・柏市エリアの省エネ地域区分
地域ごとに求められる断熱性能は、日本を8つの地域に区分することで規定されています。
千葉県はほとんどが6の地域に該当しますが、5や7も混在するエリア。八千代市が5の地域、千葉市と柏市は6の地域に区分されています。
5・6・7の地域に推奨されているUA値は0.87 W/m2K。このUA値は、住宅性能表示では等級4に相当しますが、ZEH基準で考えれば断熱等級5に同等するUA値0.6 W/㎡Kを目指したいところ。住宅ローンに有利な長期優良住宅に認定されるためには、等級5が満たすべき基準となっているからです。
そのため、千葉市・八千代市・柏市エリアでは、断熱性能等級5を満たした家づくりをおすすめしています。
千葉市・八千代市・柏市エリアの地震情報

千葉県全域が首都直下地震緊急対策区域に指定されていることからも、千葉市・八千代市・柏市エリアで注文住宅を建てるなら耐震性能を重視した家づくりが必須。耐震等級3以上を目指した家づくりがおすすめです。
>>建てる前の地盤も安心、R+house八千代・幕張・柏の地盤改良技術
>>柏市の災害リスクや家づくりに適したおすすめエリアについて詳しくはこちら!
>>八千代市の災害リスクや家づくりに適したおすすめエリアについて詳しくはこちら!
>>建てる前の地盤も安心、R+house八千代・幕張・柏の地盤改良技術
>>柏市の災害リスクや家づくりに適したおすすめエリアについて詳しくはこちら!
>>八千代市の災害リスクや家づくりに適したおすすめエリアについて詳しくはこちら!
千葉市・八千代市・柏市エリアの基準風速
基準風速とは、過去の台風記録から50年に1度の大型台風を想定し、30m/秒~46m/秒までの範囲内で国交省が定めた基準。建物の設置状況や高さ、その他係数により風力圧を算出するための数値です。基準風速の1.5~1.8倍の最大瞬間風速に耐えられることが想定されています。千葉県は千葉市が36m/秒、八千代市と柏市は34m/秒と設定。日本の中では、高い基準となっています。令和元年の房総半島台風のように、千葉エリアでは強風対策をしなければ被害発生を防ぐことはできません。
千葉市内の花見川区幕張周辺・八千代市・柏市エリアで家を建てるなら、高い耐久性能・維持管理性能を目指すことがおすすめです。
千葉市内の花見川区幕張周辺・八千代市・柏市エリアで家を建てるなら、高い耐久性能・維持管理性能を目指すことがおすすめです。
注文住宅はR+house八千代・幕張・柏・守谷にお任せ!